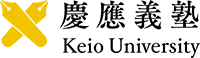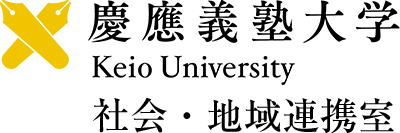神奈川県 KANAGAWA
神奈川県川崎市
新川崎タウンキャンパスは、2000年に川崎市との協働により「新川崎・創造のもり」に設置され、産官学連携の拠点として先端研究の推進、新産業・新事業の振興を進めている。具体的には、ロボティクス、環境、エネルギー、自動運転などの分野で19の 研究プロジェクトを実施(2024年度)し、各研究プロジェクトが生み出す多様な研究成果を企業等が有する資源やニーズと連携させて、新たな技術や産業の創出を図り、ベンチャー企業も誕生している。また、川崎市との連携のもと、企業、研究機関、市民等を対象としたオープンセミナーを開催して成果の一端を紹介している。(2024年度は、サイエンスカフェ、高校生向け見学会、対面式セミナーと、計3回開催した)さらに、児童を対象とした「科学とあそぶ幸せな一日」など、科学技術の学習機会やその面白さを体感できる場を提供している。
続きを読む>>
詳細ページへ神奈川県川崎市
再生医療の社会実装が直面する政策的・社会的課題を解決すべく、神奈川県川崎市川崎区殿町地区および東京都大田区羽田地区に、再生医療・細胞治療の実用化および世界展開を加速するためのプラットフォーム「殿町・羽田再生医療拠点(英語名称:Cluster for Regenerative Medicine in Tonomachi Haneda、略称:CReM TONOHANE)」が2024年6月に形成されました。アカデミア、企業、公的研究機関、自治体が集積し、産官学連携による横断的な研究開発と医療機関での医療データにより、エビデンスに基づく有効性・安全性が担保された再生医療・細胞治療を国内外で展開することを目指します。
具体的な活動は以下の通り。
・Quality by Designに基づくiPS細胞/MSCの拡大培養
・原材料から最終製品迄の品質を確保し、再生医療の付加価値を高める多様な評価法の開発
・学会等での発表、主催・共催シンポジウムの開催やウェブサイト(https://crem-tonohane.jp/)による外部発信
※慶應義塾は、研究開発のほか、拠点の運営委員会議長と事務局を務めています。
続きを読む>>
詳細ページへ神奈川県横浜市港北区
2027年度に横浜で開催される国際園芸博覧会GREEN×EXPOに向けて、暑熱環境下における熱中症リスクを低減するための行動変容モデルの提案を目標として活動を展開した。2024年度は、港北区役所の土木事務所の協力のもと、屋外の炎天下で土木作業をする職員の作業中の熱中症リスクを可視化・分析し、リスク低減に向けた仮説構築を実施した。
9月初頭の快晴日において終日作業に取り組んだ9名の職員のうち、主に年代の異なる3名の職員の心拍数や位置情報のデータを取得すると同時に、温湿度・地表面温度等の環境データを取得した。結果として、特に地表面温度が高まる環境下における作業中の負荷が大きいことが心拍データの上昇から確認されると同時に、適切なタイミングで休憩を取ることで負荷の軽減が実現されることが確認された。
続きを読む>>
詳細ページへ神奈川県藤沢市
2007年に、独立型自家用専用水道「地下水膜ろ過システム」を用いた地下水供給システムが稼働開始しました。2020年4月までは井水を飲料用および雑用水に使用していましたが、新型コロナウィルス感染拡大の影響によるキャンパス閉鎖以降、水道使用量が著しく減少したため、井水は雑用水系統でのみの使用としました。2022年5月より水道使用量が回復してきたため、飲料用としても再開しました。2024年度の実績では、年間約26,800㎥程度の井水を利用しています。
続きを読む>>
詳細ページへ小田急電鉄株式会社、神奈川中央交通株式会社
旅客輸送におけるレベル4自動運転の実現に向けて、神奈中交通と慶應義塾大学間で共同研究の覚書に基づき、湘南藤沢キャンパス(SFC)の循環シャトルバスの自動運転システムの運用、課題抽出、システム改善、評価を推進。
続きを読む>>
詳細ページへ神奈川県藤沢市
慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス(SFC)は、1990年4月の開設以来約30年にわたり、地域の様々な方々ともに、湘南の地域や文化を尊重しながら未来を先導するさまざまな研究・教育・開発を行ってきました。 SFC30年の節目を迎えた2020年、SFC研究所と湘南地域の5自治体(藤沢市・鎌倉市・茅ヶ崎市・逗子市・寒川町)はこれまでの蓄積や実績をもとに、今後とも様々な活動を協働で展開していくことを念頭に「湘南発のより豊かな未来都市」の実現へ向けた連携協力協定を締結しました。 同時に、SFC研究所の研究コンソーシアム制度のもと、「湘南みらい都市研究機構」を発足させ、産官学金民などの多様な主体へ呼びかけ、相互連携の強化に加え、未来を共創する研究開発を促進する体制の構築に取り組んでいます。慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス(SFC)は、1990年4月の開設以来約30年にわたり、地域の様々な方々ともに、湘南の地域や文化を尊重しながら未来を先導するさまざまな研究・教育・開発を行ってきました。 SFC30年の節目を迎えた2020年、SFC研究所と湘南地域の5自治体(藤沢市・鎌倉市・茅ヶ崎市・逗子市・寒川町)はこれまでの蓄積や実績をもとに、今後とも様々な活動を協働で展開していくことを念頭に「湘南発のより豊かな未来都市」の実現へ向けた連携協力協定を締結しました。 同時に、SFC研究所の研究コンソーシアム制度のもと、「湘南みらい都市研究機構」を発足させ、産官学金民などの多様な主体へ呼びかけ、相互連携の強化に加え、未来を共創する研究開発を促進する体制の構築に取り組んでいます。2024年度はこれまでの各地域との連携活動を継続する一方で、新たな地域との連携活動を行いました。藤沢市遠藤地区では中学生の放課後の勉強を支援する活動に大学生がボランティアとして毎週参加。また鎌倉市が「中高生の居場所」として開設したCOCORUかまくらに、大学生がユースサポーター(ボランティア)として参加。茅ヶ崎市湘南地区では地域の皆さんが緩やかに集える場づくりの一環として、映画上映会を開催。続いて野外上映会も開催しました。上映会の実現には地域の多くの方々にご協力いただきました。会場では「こうして地域の皆さんと一緒に映画を観られて嬉しい」と、初めて会う人同士でも会話が弾んでいました。
続きを読む>>
詳細ページへ神奈川県横浜市
市民の防災意識向上のため、防災に市民科学と参加型アートを組み合わせた防災活動の枠組みを構築し、その活動を支援するデジタルツールを開発した。提案する活動の枠組みは、①災害リスクと防災行動をアート作品で表現するワークショップの実施、②作品のインターネット展示、③作品の鑑賞からなる。市民の参加者によるワークショップを実施し、デジタルツールの有効性を検証した。
続きを読む>>
詳細ページへ